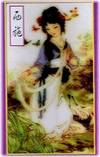アロマテラピーはフランスを発祥としていますが、日本には平安王朝から脈々と受け継がれている香りの文化「香道」があります。
日本における香りの始まりは、仏教の伝来とともに広がっていきました。
仏前を清め邪気を払うために、そして厳かな香りを仏様への奉げものとして「香」を用いていました。
『日本書紀』に「ひと抱えもある大きな沈水香木が淡路島に漂着し、島人がそれと知らずかまどに入れて薪とともに燃やしたところ、その煙が遠くまで薫り、これを不思議なこととしてこの木を朝廷に献上した」と記されています。
沈香は東南アジアに生息するジンチョウゲ科の樹木ですが、生息している木が香るのではなく、長い年月の中で、風雨や病気・害虫などから自衛手段として、木の内部に樹脂を分泌、蓄積したものが沈香となります。木でありながら水に沈むことに由来しています。
奈良の正倉院には国宝級の沈香木が所蔵されています。
正式名称は「黄熟香(おうじゅくこう)」と言いますが、一般的には「蘭奢待(らんじゃたい)」と呼ばれ、その名に「東大寺」が隠されているといわれています。
この香を手に入れることは天下人の証であり、その切り口には下賜された人の名が記された札が貼ってあります。
これまで足利義満、足利義教、足利義政、織田信長、明治天皇らが切り取っています。
宗教的儀式から始まった香りの歴史は、平安時代には貴族のステイタスとして日々のくらしの中で香りを楽しむようになってきました。
衣服に香を焚きしめる衣香(えこう)や、部屋に香りをくぐらす空薫物(そらだきもの)は貴族のたしなみであり、外国から入ってくる上等な香を炊けるのは権力の象徴でもありました。
源氏物語、枕草子をはじめ、王朝文学には香りの記述が多く見られます。貴族の生活の中で、香を焚くということは、生活の一部でもあったわけです。(続く)
![]() お肌の10秒チェックで冷え・疲れもわかる (スキンケア ハンドブックもれなく プレゼント!)
お肌の10秒チェックで冷え・疲れもわかる (スキンケア ハンドブックもれなく プレゼント!)